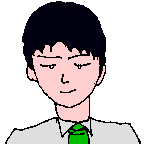 それは私、和田信也がまだ入社する数年前のこと…。
それは私、和田信也がまだ入社する数年前のこと…。
とある居酒屋で中年男性3人が安い酒を飲みながら談笑していた。
話の中心は、丸顔小太りで背はあまり高くなく、頭が薄くなった30代後半の男性。名を曽根昭という。
彼は橋桁の構造解析を行うプログラムの会社に勤めていたが、酒癖の悪さから上司と喧嘩をして会社を飛び出したばかりだった。
その飛び出すとき、彼の勤務していた会社の後輩を一緒に誘い、新会社設立の相談をしていたのだ。
その後輩の名は水上順。やせ細って、見るからに貧弱そうで、口数の少ない男に見える。黒ブチのメガネが特徴で、お笑いのMr.オクレに風体がよく似ている。彼の役割は曽根の話をだまって頷くばかり。
もう一人の男は30代前半の男性、名を木藤浩次という。
彼は、偶然この居酒屋に居合せた客だったが、隣でコンピュータの話をしているので興味を持って話に参加してきたのだ。
彼はホテルのPOS(システム)を担当したことがあり、現在はその口のうまさから同じホテルのフロント主任をしていた。
一見人当たりの良さそうな彼は、2人の話に興味をもち、会社設立の運命をともにすることに決めたようである。
これが、株式会社イースト・ソフトの始まりである(本文中ではイーストと呼ぶことにする)。
まだ株式会社を安価に設立できたころ、彼ら3人はさっそく、法人手続きをし、わずか10畳ほどの事務所を日本橋に開設したのだった。
イースト初期のころの仕事は出向がメインで、事務所にはいつも人がいなかった。皆、他の会社の組織に組み込まれ、その会社のプログラムの仕事をしているからだ。出向とか派遣とかいえば聞こえはよいが、いわゆる人買いに状況は近い。
主な出向先は大手か中堅の建設会社。その会社のプロジェクトを担っていたのだ。
その後、社員も増え、事務所も飯田橋に移し、順調に業績を伸ばしていき、6年でCAD系の仕事では少しは知られるようになった。
ただし、事務所にいる社員は事務員と社内に仕事を持ち帰っている社員数名であった。大多数の社員は出向に行っており、不在だったのである。この当時の社員数は15名程度。
そんな折、私は入社したのだった。ときは1987年の春、23歳だった。
当時、プログラムに絶対の自信のある私は、この会社なら天下を取れると目算してのことだ。
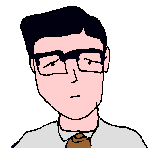 「君はできるから…」という理由で社員研修も行わず、入社初日から水上部長に引っ張られるように連れて行かれたのが、サンシャインビルにある外資系のCADメーカーで、マトラ・データビジョン。
「君はできるから…」という理由で社員研修も行わず、入社初日から水上部長に引っ張られるように連れて行かれたのが、サンシャインビルにある外資系のCADメーカーで、マトラ・データビジョン。
この仕事は出向ではなかったが、既に設計はある程度終了しており、私に与えられた作業はCADのオペレーションを覚えるという単純なものだった。
まぁ、いきなりシステムのプログラムをさせるのも無謀だということだろう。
そんな単純作業に飽きた私はある日、イタヅラでそのCADシステム(ユークリッド)のプログラムマニュアルを読みながら、幾つか実験プログラムを書いてみた。マニュアルは私の不得意な英語…。
ユークリッドは当時では珍しいソリッドモデルの3次元CADシステムで、図形構造も難解さを極めていた。また、座標系もヨーロッパ方式なので、頭が混乱したのを今でも覚えている。
しかも、日本の担当者もユークリッドのマニュアルというか、内部のプログラムの内容を良く知らず一緒に実験プログラムを書き、動作とマニュアル記載のサブルーチン推測を良くしたものだ。つまり、その当時のマトラ社は日本法人を設立したばかりで、そのプログラム構造を知っている人は遠く本国にいた。
システム記述言語はFORTRAN。唯一頼りになるのは、英文マニュアルで、システムのデータ構造とグローバル変数、それにサブルーチン仕様書から構成されていた。
従って、誰もそのサブルーチンを使用したことがないので、小さな実験プログラムを書いて、内部動作を推測するしかなかったのである。
そんな雰囲気もあって、私も実験プログラムを書いたのだった。
プログラムには、推測という能力も必要で、プログラム設計者が何を意図して製作したか?を類推する場面も多い。
そんな中で、「ああ、やっぱり」と言えるか、「なんだこりゃ」と言えるか、「なるほど」と言えるか、が技術屋として大切な要素だと思う。間違っても、「理解不能」などと思ってはいけない。
どんなに変わったシステムでも、コンピュータ上のシステムは人間が作ったという大前提が存在する。人間の作ったシステムに理解不能はありえないのだ。
もちろん物理的な要因のことをいっているわけではない。
私は会社に就職するまで多少なりともコンピュータに興味をもってきた。しかし不幸な事に当時はコンピュータの文献なんて数えるほどしかなかったし、コンピュータの事を聞ける人も身のまわりに存在していなかった。
したがって、そのような状況下では、当然、独学でコンピュータを理解するしかなかったのだ。
幾つかの「なるほど」を繰り返し知識を得、幾つかの「なんだこりゃ」を繰り返しポリシーを磨き、幾つかの「ああ、やっぱり」を繰り返し自信を得た。
幸い社会人になる前には時間がたくさんあった。だから、独学のコツは掴んでいる。どんなに難しく、新しいシステムに出会っても基本は同じだ。
幸運な事に初めての仕事は、自己の能力を表現できる稀有なパターンだ。いや良く考えると幸運じゃないし、稀有でもない。
常に自己をアピールできるよう、密かに鍛錬しているから、稀有も良くだし、幸運も実力なんだと思う。
そんなわけで、3週間後には水上部長も仕事を回してくれるようになった。つまり、マニュアル記載の推測が正しいのか?を本格的にチェックするプログラムだ。
水上部長は、悪い意味で誰が見ても技術者というような風貌で、私が話すときにはいつも苦労をした。
ただ私は性格はどうであれ、技術者としては尊敬できると思っていた。しかし周りの社員には評判が良くないようで、「一緒にいると疲れる」との評価だった。
私に言わせれば、周りの社員の技術力が低いからで、水上部長には非はないと思う。
当時の私は自信過剰だったのだ。
そんな水上部長との仕事は、これ1回きりで終わったのであった。
このプロジェクトを通して社内的に評価を得た私は、自身の仕事をメインで受け持つ立場に変わったからだ。
またあるとき、曽根社長の火を吹いたプロジェクトを無事解決してやったのも一因だろう。実際には人材不足が第一の原因だ。
曽根社長は社内に人がいないときでも平気で仕事を請け負ってくる。これは良い事だと思う。
ただし、社内に人がいないとわかると、別な解決法を模索しないで、「俺がやる!」と言って問題を先送りにしてしまう。
しかし、痩せても枯れても社長職、俺がやるひまなど作れるはずが無い。結局納期が近づくと慌てて、「誰か、これやって」となってしまう。
過去にも何人かの被害者がでたようだ。通常は短い納期で納品できるわけでもないし、自分の仕事もあるのでプロジェクトは火を吹いたまま進行する。
ところが私は仕事が速かった。人に言わせると、尋常なスピードじゃないらしい…?
当時は社内の人材不足を隠すように、「社員全員SEかつプログラマー、プログラムの頭脳集団」が会社のキャッチフレーズだった。
つまり、社員各人が分析、設計をし、作業も行う。個々人に、プログラム生産全ての能力を身につけて欲しいということだろう。
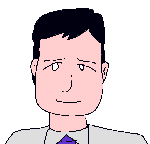 ちなみにイーストの社員構成は、曽根社長と2人の専務(水上と木藤)が年配組みで、その他の社員は全て若い。年も私と同じ位の人が大部分だ。
ちなみにイーストの社員構成は、曽根社長と2人の専務(水上と木藤)が年配組みで、その他の社員は全て若い。年も私と同じ位の人が大部分だ。
他の社員は2年制の専門学校を卒業した分、私の先輩社員となっているに過ぎない(大多数が私より1歳下)。
見渡して見て年配の社員は、私達より5歳ぐらい年が上の人で吉田賢治という体格の良い人と、得体の知れない35歳ぐらいの社員がいるだけである。
それにしても、年配の社員が会社の歴史を経て残っていないという事はどういうことだろう?
その原因がわかるのはまだ先のお話。
そのような経緯があって、入社して3ヵ月した夏になるころ、大きな設計を経験したことが無い責任者に私の立場は変わっていた。
チーム開発のノウハウや作業の進行方法、見積りなどを、完全に独自で解決しなければいけない羽目になったのだ。
同期入社の2人は出向に出され研修しているし、他の社員も聞けるような人物がいない。
しかし、会社のレベルが低かったのかといえばそうでもない。
出向といっても、出向会社のCADシステム(インターグラフや上記のマトラ)のグレードアップや管理運用をメインで行っていた当時では日本で数少ない会社だったのだ。
良い表現で言えば、若いが、力のある将来性のある会社だ。
バブル崩壊後、出向に頼っていた会社が簡単につぶれていった現実を見ると、曽根社長の方向性も当時では間違っていないと思う。
小さくて若い会社だが、可能性だけはひたすらあったのだ。