水上部長がイーストを去ってから社内では、ますます技術力低下が蔓延していった。しかし、Drawingの売上は好調だし、技術部の受注も順調だった。
木藤専務にしても、水上さんが抜けたことによって社長に意見が通りやすくなり、木藤専務の発言力が増していった。
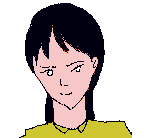 そんな折、Drawingのコンパニオンをしていた佐伯慶子がイーストに入社する事になった。
そんな折、Drawingのコンパニオンをしていた佐伯慶子がイーストに入社する事になった。
これは木藤専務の推薦で、Drawingのショーがある時に便利だというのが理由だ。
待遇はアルバイト扱いで、配属は営業部だ。しかし、アルバイト扱いとはいえアルバイト料はかなり高額だった。もちろん、本業であるDJの仕事は続けている。DJは深夜と日曜担当なので可能なのだ。当然、その行為はイースト社員の批判を浴びた。
また、ある営業マンの為に、横浜に営業部の分室を開設した。この事実は一部の社員しか未だに知らないことだ。その部屋が使われたのかどうかは誰も知らない。もちろん私も…。
これは完全に木藤専務の独断で決定された。
ただ言えることは、この時点でイーストには事務所が4ヶ所あるということだ。
更に言うと、社員数が40名程度なのに対して事務所が4ヵ所あるということだ。
この情報を知った私は次のように思った。
「こんなに事務所が出来ては、地元に事務所を引っ張る計画が危うい」という考えと、「今なら地元に事務所を作れるかもしれない」という考えだ。
おそらく、木藤専務の意見で話は決まるだろう。
横浜に事務所ができた影響をどう読むのか?ということである。
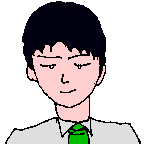 その頃の私は相変わらず自由奔放に振舞っていたので、責任感を問われればマイナスイメージだ。
その頃の私は相変わらず自由奔放に振舞っていたので、責任感を問われればマイナスイメージだ。
それはそうだ。こんなことをしている人に人材を任せられないってのが一般的な考えだ。私もそう思う。
しかし、私が根っから自由奔放に振舞っていたのかというと違う。
プロジェクトによってはイーストの社員を使うときもあるのだ。
そのときの私は、きちんと出社し、仕事も納めた。言い訳にしか過ぎないだろうが…。
徳田も面白い。彼は人を寄せ付けない部分があるが、社員を割り振られると親切に指導をした。
つまり、私も徳田も責任感は人一倍あるようだ。仕事をきちんと納めるのも責任感の行使の現れだ。ここが長井チームをはじめイースト社員と違う。
世間一般からは当たり前のことだが、イーストでは当たり前でなくなってきているのだ。
このような状況を踏まえて、私はシミュレーションしてみた。
もう2年ほど自由を謳歌するか、思いきって会社を去るかの両極端のパターンだ。
このときの私は27歳…。技術者として踏ん切りをつけなければいけない一つの目安として、私が設定していた年齢でもある。これ以上の年齢で地元に帰って勝負するには辛いと思っていた年齢だ。
しかし、シミュレーションの結果、もう一つインパクトが無いのだ。
何故なら、理由はどうであれ、会社に来ない人物という事実が、会社を動かすほどの評価にあたらないと思えるからだ。
この事実を打ち消すような方向に持っていかなくてはいけない。
幸い木藤専務は、私をある程度責任感があり、人を使えると私を見ているふしがある。問題は社長だった。
そんなことを考えている時に1つの仕事が舞い込んだ。
業界のモルモットと呼ばれている、某家電メーカーの開発したCAD用入力機器の為にソフトを書いてくれというものだ。
その機器は単なる液晶タブレットと同一の機能なのだが、700万円もする高価なしろもので、良いソフトが無いと売れないという見解だった。
しかし、その機能は液晶タブレットの比ではなく、とにかく大きい。さすが、業界のモルモットと言われるだけのメーカーだ。
しかも表示部分は、レーザー描画(いわゆるテクトロ)仕様だった。
このプロジェクトはDrawingと鈴木建設をも巻き込んで、開発期間を半年程度、費用2,000万円でイーストが請け負う事になった。
もちろん、私1人での開発だ。人月でいうと300万円以上の仕事量になる。
これはチャンスだ!とっさに私は思った。社長の考えを動かすには現金が絡むと良いのだ。
長井部長が咎められないのも、Drawingが売れているからだ。
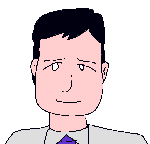 会社に対して、「地元に会社事務所を設立してください…」とお願いすると、私が頼んだ形になり後々不利だ。恩をきせられてはたまらない。
会社に対して、「地元に会社事務所を設立してください…」とお願いすると、私が頼んだ形になり後々不利だ。恩をきせられてはたまらない。
そこで、ある計略を実行に移した。
いつものように吉田部長を酔楽に呼び出して、「私は会社を辞めて地元に帰ります」と宣言した。
吉田部長は「そうか…いつかそう言うと思っていたよ、決心は固いのか?」と聞いてきた。
一度宣言したらもう後には引けない。サイは投げられたのだ。
「ええ、もう良い歳ですし…」
「そうか…」と吉田部長は答えると、会社に電話をかけ木藤専務を呼び出した。
数分後、木藤専務が酔楽にやってきた。
席に座ると、木藤専務は余計なことを言わずに、「和田君、いつか地元に事務所を開く話があったよね?」と切り出してきた。
そうだ、折に触れて私が発言してきたことだ。
続けて、「先ほど社長とも話していたんだが、来年実現するよ」と返答してきた。
おそらく、酔楽に来る道すがら考えていた台詞だろう、あっさりと私の思惑通りになった。
余計な戦略が必要無くなった私は、会社を辞めるという言葉を早いうちから撤回するタイミングの勝負となってしまった。
計算では、吉田部長と木藤専務が私への説得の後に事務所の話が出る予定だったが、意表をつかれた形だ。もちろん、話の展開では会社を去ることも視野に入っていた。
私が答えに窮した瞬間に、吉田部長が「和田、だったら辞める必要は無いよ。和田だったら向こうでもうまくやっていくよ」と言ってきた。
出社拒否症の吉田部長が出社拒否の私に「うまくやれるよ…」とは面白いと感じたことを今でも覚えている。
すると木藤専務が「そうだよ、もうこれで和田君も決まったね」と頷いていた。
私が「ええ…」と返答しているその時に木藤専務が「湯川君を呼んで飲もうよ」と言ってきて、「よかったね」と言葉を続けた。
すると吉田部長は湯川を呼ぶために会社に電話を入れ、その後湯川がやってきた。
結局、私が何か答えるまでも無く話は解決してしまったのである。私が言った言葉は「ええ…」ぐらいだ。
しばらくすると湯川がやってきて、いつもの飲み会になっていた。
まるで私の話など無かったようにだ。
新規プロジェクトを東京で仕上げたら「あの話は無かったことに…」なんて言われるんじゃないかと言う懸念を抱かずにはいられなかった。
それは私がもうすぐ28歳になろうとしている1991年の秋のことだった。